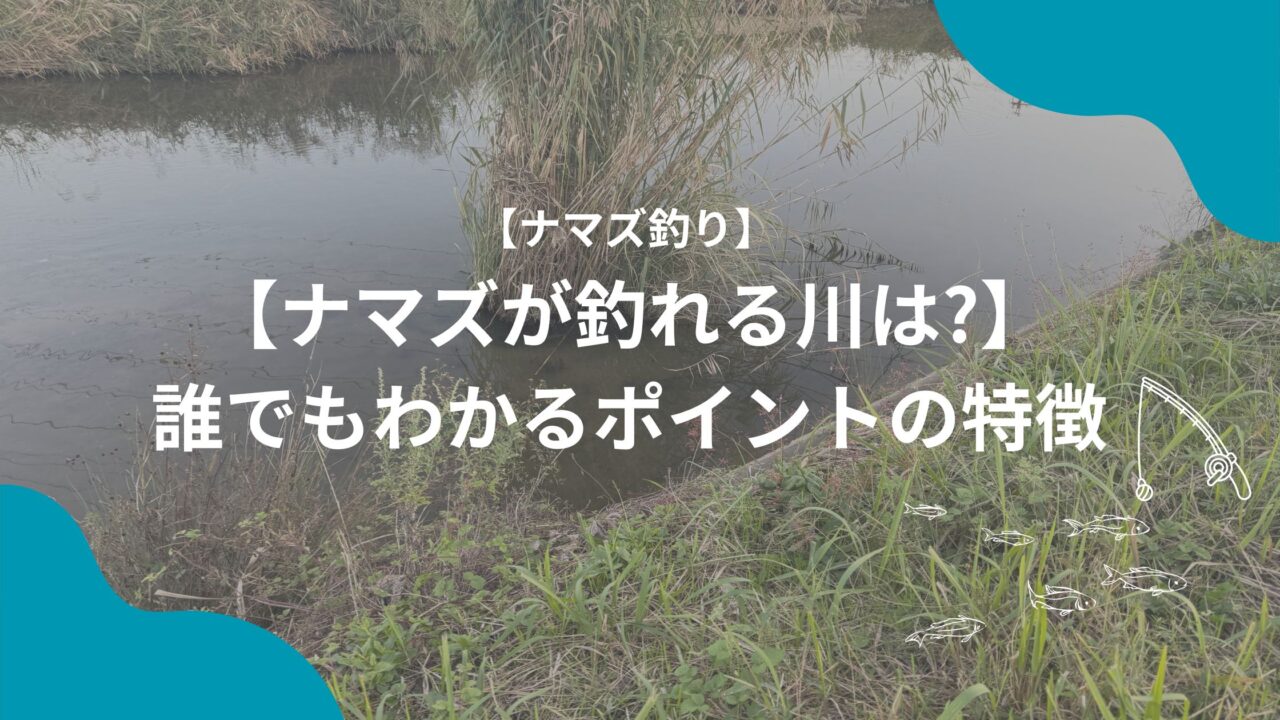「ナマズはどんなところにいるの?」
「ナマズが好むポイントはどこなのか?」
そのように思ったことはないでしょうか?
この記事では、ナマズ釣りを始めたけど、どんな川にナマズがいるのか、またナマズが好むポイントなどを紹介しています。
ぜひ参考にしてナマズ釣りに挑戦して、思い出に残る一本を手にしてください。
ナマズが釣れる川の選び方
ナマズはこんなところにいる!
ナマズは日本各地の川は用水路に生息していますが、環境やポイントによっている川といない川に別れます。
また、「流れが緩い」「エサが豊富」「隠れ場所が多い」などの環境を好むため、見極めが重要。
ここでは、実際にナマズが生息する川とそうでない川の特徴を比較してみましょう。

生息している川
ナマズが好むのは、流れが緩やかで泥底が広がる中〜下流域に生息しています。
また、カエルや小魚などのベイトが豊富な環境であることもポイントの一つです。
代表的な特徴は以下の通りです。
- 水深1〜2m前後の浅場がある
- 近くに田んぼがあり用水路と繋がっている。
- 橋脚・護岸・葦(アシ)などのストラクチャーが点在する。
- 水温が安定していて濁りがややある。
水深1〜2m前後の浅場ある
ナマズは深すぎる場所よりも、浅場を回遊しながらエサを探す傾向があります。
体が隠せるほどの水深(1〜2m前後)があれば十分で、夜になるとさらに浅場に上がっていきます。
近くに田んぼがあり用水路と繋がっている
田んぼが隣接している場所は、カエルや小魚などのベイトが集まるため、ナマズにとっての”食堂”のような存在。
また、流れ込みなどがあれば、酸素量も増えて活性が上がります。
橋脚・護岸・葦(アシ)などのストラクチャーが点在する。
ストラクチャー(障害物)はナマズの隠れ家。
日中はこうした影や障害物の下に潜み、夜になると警戒心が薄くなり、活発に行動するようになります。
こうした変化のある場所は、特にバイトが出やすいポイントです。
水温が安定していて濁りがややある。
ナマズは急な水温変化を嫌い、また視覚よりも音や波動に反応します。
やや濁りのある川はプレッシャーが低く、身を隠せるので安心できる環境です。
クリアすぎる水よりも釣りやすい傾向にあります。
生息していない川
ナマズがいない川には、いくつの共通点があります。
主に「水温が低い」「流れが速い」「隠れ家(ストラクチャー)がない」環境です。
- 渓流や上流域など冷たい水温
- コンクリート護岸ばかりで隠れる場所がない
- エサとなる生き物がいない

渓流や上流域など冷たい水温
冷水域ではナマズの代謝が落ち、活動が鈍くなります。
特に水温が15℃以下の環境では、ほどんど行動しないため釣果は期待できません。
コンクリート護岸ばかりで隠れる場所がない
隠れ場所の少ない護岸ばかりの川では、ナマズが安心して休むことができません。
天敵から身を守る場所がないため、定着しにくい環境です。
しかし、下流や上流に葦(アシ)などのストラクチャーや周りに田んぼがある場合は、ナマズがいる可能性があるため、その一部分を見るのではなく周りを見る必要があります。
エサとなる生き物がいない
ナマズは雑食性で、主な捕食対象は「小魚」「カエル」「虫類」など。
こうしたベイトが少ない川では、ナマズにメリットがないため、生息しません。
どんなポイントが狙い目?
同じ川でも、ナマズが潜む”ピンポイント”を探すのが釣果のアップのコツです。
その中でも代表的なポイント4つ紹介します。
ナマズ釣りでどのポイントを狙っていいのかわからない方はこの4箇所を中心に攻めてみてください。
流れ込み
ナマズ釣りでは超一級ポイントです。
”カエル”や”虫”などナマズのエサが落ちてくるのを待ち伏せできるのでルアーを落とすだけで釣れてします。
しかし、一級ポイントで他のアングラーも狙うため、プレッシャーが高い場合があります。
近づく場合は足音などをなるべく立てないよにし、プレッシャーを与えないようにしましょう。
ナマズがいれば、何か反応があるので流れ込みを見つけたらルアーを投げてみてください。
葦(アシ)の中
葦際は、ナマズの絶好の隠れ家。
昼間は身を潜め、夜になると捕食のために外に出てきます。
ルアーを際ギリギリに通したり、軽く止めたりするのがコツです。
また、葦の中に入れるのもおすすめの釣り方です。
葦の葉が濃いところや、草の向きによってルアーが引っかかってしまうので注意が必要。
あまり濃くなく、草の生える向きがこちらを向いている場合は引っかかる確率が低いので、葦の中に直接キャストして狙ってみるのも効果的です。
他のアングラーが狙ってなくプレッシャーも少ないので釣果がアップするかもしれません。

駆け上がり
浅場と深場の境目は、ナマズがエサを待ち伏せせする場所。
深場で身を隠し、浅場に来た小魚などを追い込み捕食します。
駆け上がり付近を違う角度から何度も通して反応を探ってみましょう。
堰下(せきした)
堰や落差工の下は水流が複雑で、酸素が豊富です。
また、上流からエサが流されてくるのでナマズが溜まりやすく、人気のポイントとなっています。
流れのヨレや、深くなっているところにルアーを通して探りましょう。

壁際
護岸沿いは意外と見落としがちですが、ナマズがいる可能性が高いので見逃せません。
周りが田んぼで囲まれていたりすると、カエルなどが落ちてくるのを狙って待機しています。
壁沿いにルアーをキャストして、巻くだけでナマズが反応してくれます。

| ポイント | 特徴・狙い方 | コツ・注意点 |
|---|---|---|
| 流れ込み | カエルや虫など、上流から流されてくるエサを待ち伏せできる超一級ポイント。ルアーを落とすだけで釣れることもあります。 | 人気ポイントのためプレッシャーが高い。近づく際は足音を立てず、静かにアプローチするのがコツ。反応がなければ角度やルアーを変えてみましょう。 |
| 葦(アシ)の中 | 昼間は身を潜め、夜になると捕食に出るナマズの隠れ家。葦際や中にルアーを通すとヒット率が高いです。 | 濃い葦や逆向きの草はルアーが絡まりやすいので注意。比較的まばらな場所や、自分側に草が倒れているところを狙うと効果的。 |
| 駆け上がり | 浅場と深場の境目。ナマズは深場で隠れ、浅場に来た小魚を狙って捕食します。 | 一度で反応がなくても、角度を変えて複数回ルアーを通すことでヒットチャンスが増えます。 |
| 堰下(せきした) | 落差工や堰の下は水流が複雑で酸素が豊富。上流からエサも流れ込みやすく、ナマズが溜まりやすい人気ポイント。 | 流れのヨレや深みを重点的に攻めましょう。流れが速い場合は、ルアーを沈めすぎないように調整します。 |
| 壁際(護岸沿い) | 見落とされがちですが、実は好ポイント。田んぼが近い場合はカエルなどが落ちてきやすく、ナマズが待機しています。 | 壁沿いをタイトに通すだけで反応が得られることが多い。ナイトゲームでは街灯付近の壁際もおすすめ。 |
ポイント選びの重要性
ナマズ釣りでは、ルアー選びよりも「場所選び」が釣果を左右します。
ナマズがいない川では、どんなルアーでも釣れません。
まずは、Googleマップで川の地形をチェックしましょう。
「流れ込み」「葦(アシ)」「堰」「橋脚」などの変化がある場所をピックアップし視察をしましょう。
視察をするときの注意点は、昼間や明るい時間帯にすること。
夜だと足元が見えず危険です。
また、水深やストラクチャーなどが見えないため、なるべく明るい時に視察はしましょう。
運が良ければ、視察の段階でナマズに会えるかもしれません。
ナマズの釣れる時期
主に春から秋(4〜10月)にかけてです。
特に産卵期前後の5〜7月は活性が高く、最も釣りやすいシーズンといえます。
水温が上がり始める春先は浅羽で活動を再開し、夏は夜行性が強まり夜釣りが効果的です。
秋になると食い溜めのために再び積極的にエサを追い、サイズの良い個体が狙えます。
反対に、水温の低下で動きが鈍くなるため、釣果は落ち込みます。
春
水温が上がりゆっくりと動き出す季節。
特に水温が15℃を越え始める4月〜5月頃になると、一気に活性が高まり、産卵を意識して浅場に姿を見せるようになります。
流れ込みや葦際、暖かい水が流れ込む場所は絶好のポイントです。
春は朝晩の冷え込みがあるため、日中の気温が上がったタイミングを狙うのがコツ。
また、雨の後などで少し濁りが入るとナマズの警戒心が薄れ、ルアーへの反応もよくなります。
季節の変わり目なで釣果にムラが出やすい時期ですが、動き始めたナマズを見つけられれば、一発大物のチャンスも十分にあります。
夏
ナマズ釣りのハイシーズン。
気温・水温主に高く、ナマズの動きも一年で最も活発になる季節です。
夜になると浅場に出てきて、流れ込みや葦際で積極的に捕食行動を取るため、ルアーへの反応も抜群。
トップウォーターで豪快なバイトシーンを楽しめます。
おすすめは、雨上がりの夜や日没直後〜深夜にかけての時間帯。
虫やカエルが動き出し、ナマズの捕食スイッチも入りやすくなります。
一方で、昼間は水温が上がりすぎるため、深場や日陰に潜んでいることが多いです。
真夏の夜に響く「ボシュッ!」というバイトおんと強烈な引きはまさにナマズ釣りの醍醐味。
暑さ対策と安全装備をしっかり備えて、思い出に残る一尾を狙いましょう。
秋
9月の終わり頃になると暑さも落ち着き、ナマズたちは冬に備えてエサを食べ始めます。
まだ水温も高く、活性も十分なので良いポイントにあたれば春と同じようにトップでの釣りも楽しめます。
ただし、この時期は田んぼの水を抜く「落水」が始めるため、用水路や支流にいたナマズが本流へと戻っていきます。
そのため夏まで連れていたポイントで急に反応がなくなることも。
本流で狙う場合は、カーブの外側、ワンド、水深のあるカバー周りなどを重点的に攻めるのがコツ。
水位が安定した小河川や、水門の変化が少ない場所を見つけると、秋でも安定した釣果が期待できます。
冬
冬になると水温の低下により、ナマズの動きは一気に鈍くなります。
特に12月〜2月は水温が10℃を下回ることも多く、捕食行動も減少。
基本的には深場や水温が安定した場所に潜み、ほとんど動かなくなります。
それでも全く釣れないわけではありません。
水温が上がりやすい午後〜夕方や、雨の後で水温が一時的に上がったタイミングを狙えばチャンスが上がります。
流れ込みや日当たりの良い浅場など、わずかに暖かいエリアにナマズが寄ってきます。
この時期はアクションをゆっくりめにして、ボトム付近をスローに誘うか、リアクションで探るのが基本。
底を意識したリトリーブやステイが効果的です。
| 季節 | 特徴 | 釣り方・狙い方のポイント |
|---|---|---|
| 春(3〜5月) | 水温が上がりナマズが活動を再開。特に4〜5月は産卵期に入るため、浅場での釣果が期待できます。 | 水温が上がり始める夕方〜夜が好タイミング。流れ込みや葦際など、水温の高いエリアをゆっくり攻めるのが効果的。 |
| 夏(6〜8月) | ナマズの活性が最も高く、トップウォーターゲームのベストシーズン。夜になると浅場で盛んに捕食活動をします。 | トップ系ルアー(ノイジー・フロッグ)が有効。夕マズメ〜夜中が狙い目で、水面の“ボシュッ!”というバイトが魅力。 |
| 秋(9〜11月) | 暑さが落ち着き、ナマズが冬に備えて活発にエサを取る時期。季節の変わり目で行動範囲が広がります。 | 本流のカーブ外側やワンドなど、水深がある場所を中心に広範囲を探る釣り方がおすすめ。日中でも比較的反応が出やすい。 |
| 冬(12〜2月) | 水温低下で動きが鈍くなり、深場でじっとしている個体が多くなります。釣果は渋め。 | 日中〜夕方の暖かい時間帯を狙う。ボトム付近をスローに探り、わずかなアタリを丁寧に拾う釣り方が有効。 |
季節ごとの特徴はこんな感じ!
次に紹介するのは夜にあると快適な装備!
あると便利は装備
ナマズ釣りは夜間に行うことが多く、足場悪かったり視界が限られたりする場面も少なくありません。
快適かつ安全に楽しむためには、いくつかの装備を揃えておくことが大切です。
ヘッドライト
夜釣りでは欠かせない必須アイテム。
両手が自由に使え得るため、ルアー交換や魚の取り込みもスムーズに行えます。
赤色ライトや調光機能付きタイプを選ぶと、魚へのプレッシャーを抑えながら快適に釣りができるでしょう。
長時間の釣行に備えて、予備の電池や充電器を用意しておくのも忘れずに。
ライトを点灯させる時は、なるべく水面を照らさないよにしましょう。
ナマズが驚いて逃げてしまいます。
もしくは、赤色のライトにすればプレッシャーを与えずにすみます。
赤色は魚が認識しにくい色となっているので覚えておきましょう。
ランディングネット
岸際や足場の高いポイントでは、ネットがあると安心感が違います。
特にナマズはパワフルに暴れるため、ラバータイプのネットを選ぶとフックが絡まりにくく扱いやすいです。
また、ネットの柄が長めのタイプを選ぶと、足場が高い場所でも安全にキャッチできるのでおすすめです。
まとめ
ナマズ釣りを楽しむ上で大切なのは、「川選び」と「ポイントを見極める」こと。
ナマズは気まぐれに見えて、実は生息環境や川の流れなどに敏感な魚です。
流れ込みや葦際、堰下などの”ナマズが潜みやすい場所”を丁寧に探ることで、釣果は確実に変わってきます。
夜の水面を割るあの「ジョボッ!」「ボシュッ!」という音と衝撃は、ナマズ釣りの醍醐味そのもの。
静かな川辺でその瞬間を味わえば、また竿を持って出かけたくなるはずです。
初めてのナマズを狙う方は、まずは身近な小規模河川や用水路からスタートしてみましょう。
足場が安定していて、街灯がある場所なら安全に釣りを楽しめます。
マナーを守り、無理のない範囲で少しずつ経験を重ねていけば、きっと”自分だけのナマズポイント”が見つかるはずです。